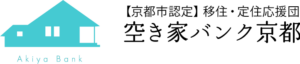- 初めてで何から始めればいいか不安
- 賃貸に出すメリットを知りたい
- 空き家を有効活用したい
知識もなく空き家を賃貸に出すと、想定外の初期費用や借主トラブル、法律違反などの思わぬリスクに直面する恐れがあります。そのため、空き家を賃貸に出す際に知るべき知識を身に付けておくことが大切です。
今回は、空き家を賃貸に出す際の基礎知識から主なステップ、関連する法律・税金、借主の募集方法、運用のコツなどをわかりやすく解説します。当記事を読むことで、空き家を安全かつ効果的に賃貸活用し、収益化への第一歩を踏み出すことができるでしょう。 ぜひ参考にしてみてください。
空き家を賃貸に出す前に知るべき基礎知識
空き家を賃貸に出す第一歩として、所有者が知るべき基礎知識をわかりやすく解説します。基礎知識を知り、空き家の賃貸運用を成功させるための土台を作っていきましょう。
「空き家を賃貸に出す」ことが注目されている理由
現在、日本が抱えている深刻な社会問題の一つが空き家の増加。その背景には、人口減少や少子高齢化、都市部への人口集中、相続によって使われなくなった住宅の放置などが挙げられます。総務省の「令和5年 住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は約900万戸にのぼり、全住宅の13.8%まで増加。
こうしたなか、空き家を有効活用する手段として、賃貸活用に注目が集まっているのです。空き家を賃貸に出すことで、固定資産税や維持管理費の負担を抑えつつ、家賃収入を得られます。今後さらに深刻化する空き家問題に対し、「貸す」という選択肢は、所有者にとっても社会にとっても有効な解決策として注目され続けるでしょう。
空き家を賃貸に出す前に知るべき5つの現実
空き家を賃貸に出す際は、単に空いている家を人に貸せば収入が得られるという単純な話ではありません。以下に挙げるような「現実」を事前に理解しておくことで、失敗を回避しやすくなります。
- 【初期費用が必要】
→築古物件(築年数の古い物件)では修繕やリフォームが必須になるケースが多く、準備資金が求められる - 【借主とのトラブルリスク】
→家賃の滞納や設備破損など、トラブルの可能性は常に存在する - 【空室期間の発生】
→すぐに入居者が決まるとは限らず、数か月空くこともあるため、その間の維持費も覚悟が必要 - 【管理の手間と費用】
→自主管理には対応力が求められ、管理会社に任せると手数料がかかる - 【法律・税務の知識が不可欠】
→賃貸契約や確定申告、各種税金など専門的な知識も必要
これらを理解したうえで準備を進めれば、より安定した賃貸経営につながるでしょう。
空き家を放置すると発生するリスク
空き家を何年も放置しておくと、さまざまなリスクが発生します。最終的には所有者自身に大きな損失をもたらすことがあるため、事前に理解しておくことが重要です。空き家を放置すると、主に以下のようなリスクがあります。
| リスク | 内容 |
| 老朽化 | 老朽化による倒壊により、隣家への損害や通行人の怪我などにつながる |
| 防犯 | 空き巣や不法侵入など、犯罪の温床になりやすい |
| 火災 | ごみの堆積や老朽化した配線が原因で火災の危険性が増す |
| 景観悪化 | 荒れた外観が地域の美観を損ね、近隣住民とトラブルになる恐れがある |
| 経済的損失 | 放置による税負担や行政代執行に伴う解体費用の負担などが発生する |
空き家を放置することは、リスク以外の何物でもありません。早期に空き家の管理やリフォーム、活用を検討する必要があります。
賃貸 vs 売却|比較で知るメリット・デメリット
空き家を活用する手段のなかには、「賃貸」や「売却」があります。人によっては、どちらを選べば良いのか悩んでしまうでしょう。今回は賃貸運用と売却のメリット・デメリットをわかりやすく表にまとめたので、参考にしてみてください。
【賃貸のメリット・デメリット】
| 項目 | メリット | デメリット |
| 初期費用 | 継続収入で投資回収が可能 | リフォーム費用が発生することもある |
| 収入 | 家賃収入が長期的に得られる | 空室期間がある可能性あり |
| 管理負担 | 将来的に自己使用も可能 | 日常的な管理やトラブル対応の手間がある |
| 節税効果 | 減価償却や固定資産税などによって節税効果が期待できる | 確定申告が必要になる |
【売却のメリット・デメリット】
| 項目 | メリット | デメリット |
| 初期費用 | 費用負担は比較的少なく済む | 資産として残らないため再活用ができない |
| 収入 | 売却代金を一括で得られ、即現金化できる | 一度きりの収入にとどまる |
| 管理負担 | 所有後の管理やトラブル対応が不要で手間がかからない | 賃貸収入のチャンスを失う |
| 節税効果 | 譲渡所得税のみ | 賃貸に比べると節税効果は小さい |
短期的にまとまった資金が必要であれば売却、長期的な資産運用をしたい場合は賃貸が適しています。将来の活用方法やライフプランにあわせて、慎重に判断していきましょう。
築古物件でも貸しやすい空き家の条件
賃貸を始める前には、まず空き家の状態をしっかり確認しましょう。空き家が築古物件であっても、一定の条件を満たしていれば賃貸物件として十分に貸し出せます。主なチェック項目は、以下のとおりです。
- 基礎や柱の耐震性が確保されている
- 屋根や外壁、基礎部分に大きなひび割れがない
- 雨漏りの痕跡(天井や壁)やシロアリ被害がない
- 床の傾きや柔らかい部分がない
- キッチンやトイレ、風呂などの水回りが綺麗で使える
- 電気の配線やガスの配管などの劣化がない
- 庭の雑草や残置物などが処理されている
- 駅までの距離、スーパーや学校の有無など、立地や交通アクセスといった生活環境が整っている など
これらの条件が満たされていれば、築年数が古くても収益物件になる可能性があります。なお、建物の状況に関して自己判断できない場合は、物件状況を専門家に判断してもらうインスペクション(住宅診断)を実施しましょう。インスペクションの一般的な費用は、約5万円からです。インスペクションの実施により、将来的なトラブルを回避できるでしょう。
空き家を賃貸に出すための活用方法
空き家を賃貸に出す際の活用方法は、物件の状態や立地、需要に応じてさまざまな選択肢があります。以下に主な活用方法をまとめました。
| 活用方法 | 詳細 | 向いているケース |
| 一般賃貸住宅として貸し出す | ・居住用物件として賃貸 ・ファミリーや単身者向けなどターゲットを絞って運用可能 | ・比較的状態が良い空き家 ・駅からのアクセスがある場所 |
| 店舗・事務所として貸す | カフェや美容室、SOHOなど住宅以外の用途で貸し出し | ・商業エリアや人通りのある場所 ・ユニークな外観の家 |
| リフォームして貸す | 水回りや内装などをリフォームして家の価値を上げ、収益を高める | 老朽化しているが構造はしっかりしている物件 |
| DIY可能物件として貸す | 借主が自由にリノベーション可能、原状回復義務なしなど条件を緩くして移住者や若者向けに募集 | 手を加える余地のある物件 |
| 古民家再生・趣味向け賃貸 | 古民家を活かし、田舎暮らしやアート活動、カフェ店舗などに使いたい人向けに賃貸 | 古民家や歴史的価値のある空き家 |
| 民泊・短期賃貸 | ・Airbnb等を使って旅行者向けに短期貸し出し ・観光地やアクセスの良い立地で有効 | ・観光需要のあるエリア ・都市部の物件や別荘 |
| シェアハウス | 複数の入居者で住む形にして、空間を効率活用しながら収益を最大化 | 広い間取りや部屋数の多い家 |
それぞれの活用方法には初期費用・管理の手間・法規制(用途地域や建築基準法など)などの違いがあるため、目的に応じて選ぶことが大切です。
入居者を募集する方法とポイント
入居者募集には戦略が必要です。どれだけ良い物件でも、ターゲットに情報が届かなければ空室は解消できません。以下のような募集方法を把握しておきましょう。
| 募集方法 | 特徴 | 向いているケース |
| 不動産会社に依頼 | ・地域のネットワークを活かせる ・審査や契約手続きも代行してくれる | ・遠方の空き家、手間をかけたくない ・不動産知識に不安がある |
| 賃貸ポータルサイト掲載 (SUUMO、HOME’S、アットホームなど) | ・集客力が非常に高い ・写真や動画で魅力を伝えられる ・多くの候補者にアプローチ可能 | 自主管理でも広く集客したい |
| SNS・知人の紹介 | ・信頼あるネットワークで募集できる ・費用がかからない ・地域とのつながりも築ける | 地域密着の大家さん、身元がわかる人に貸したい |
| ジモティーなどの掲示板サービス | ・地域内で気軽に情報発信できる ・問い合わせハードルが低く、スピード感あり | 急ぎの募集、家賃を抑えたい入居希望者を狙いたい |
| 空き家バンクの活用 (自治体運営) | ・自治体が空き家活用を支援・補助金や改修サポートがある場合も ・移住希望者とマッチングしやすい | 地方の空き家、地域活性化と連動した活用を考えている |
| 大学・病院・企業へのチラシ配布・掲示 | ・ターゲット(学生・医療関係者・単身赴任者)に届きやすい ・意外とニーズが多いものの競合は少なめ | ・近隣に施設がある ・ターゲットを絞りたい |
| 地域のフリーペーパー・ミニコミ誌掲載 | ・高齢者などネットを使わない層への訴求に有効 ・地元情報と親和性が高い | ・地方かつネットを利用しない層にアプローチしたい ・ネット募集と並行したい |
とくに、自分で募集する際はターゲット(単身者・家族向けなど)に合った広告内容を選定したり、写真を多数掲載して室内の雰囲気を具体的に伝えることを意識しましょう。また、内見時にしっかりと対応し、信頼感を持ってもらうことも重要です。
空き家を貸す前にやっておくべきチェック項目
空き家をスムーズに賃貸運用するためには、事前に確認すべきポイントがあります。準備不足によってトラブルや収益機会の損失につながることもあるため、以下のチェック項目を覚えておきましょう。
| チェック項目 | 詳細 |
| 境界線と権利関係の確認 | ・土地の境界線が明確になっているか ・所有権や共有者との同意が取れているか ・登記内容に誤りがないか |
| 空き家を賃貸に出す法的可否の確認 | ・建築基準法や用途地域の確認 ・再建築不可物件ではないか ・地域条例や管理規約で賃貸制限がないか |
| 火災保険や家財保険の見直し | ・保険が空き家状態に適用されているか ・借主に必要な保険の案内ができるか ・損害時の補償内容が十分かどうか |
| 収支シミュレーションと税負担の把握 | ・家賃収入や経費などを把握 ・所得税・住民税の影響を試算 ・控除や特例制度適用の可能性を確認 |
| 管理体制・トラブル対応の整備 | ・緊急連絡先や修繕体制の明示 ・管理会社との契約条件の確認 ・入居者対応フローの事前策定 |
これらのポイントを押さえることで、スムーズかつ安全に空き家を賃貸に出すための土台が整います。
空き家を賃貸に出す主なステップ
空き家を賃貸に出すには、適切なステップで準備を進めることが重要です。空き家を賃貸に出す主なステップは、以下のとおりです。
- 現況確認
- リフォーム・クリーニングの実施
- 管理方法(自主管理 or 管理会社)の選定
- 家賃相場の調査と設定
- 賃貸借契約の準備
- 入居者の募集
- 入居者の審査
- 賃貸借契約の締結・引き渡し
上記のステップを押さえることで、スムーズかつトラブルの少ない賃貸経営が実現できるでしょう。ただし、各ステップにおいて注意点や必要書類などが異なるため、事前に全体像を把握しておくことが大切です。それぞれのステップを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
現況確認
賃貸に出す前に必須といえるのが、空き家の現況を正確に把握することです。空き家の老朽化状況、設備の動作確認、雨漏りやシロアリ被害の有無などをチェックしましょう。築年数が古い場合は、耐震性の確認も重要です。主なチェック箇所は以下のとおり。
- 屋根や外壁の傷み
- 水回り(トイレ、風呂、キッチン)の劣化
- 電気・ガス・水道の使用可否
- カビやにおいの有無
- 床の沈み込み具合
- 壁紙の汚れや剥がれ
- 基礎のクラック(ひび割れ) など
必要に応じてインスペクションを依頼しましょう。問題がなければ、借主へ安心感を与えられます。問題がある場合は、早急に対応することが大切です。
リフォーム・クリーニングの実施
現況確認の結果をもとに、必要であれば以下のようなリフォームやクリーニングを行いましょう。
| 箇所 | 判断基準 | 理由 | 費用相場 |
| キッチン・浴室・トイレ | 水回りの劣化(水漏れやつまり、異臭、老朽化など)が進んでいる場合 | 水回りは入居者が重要視する設備のため | 10~150万円 |
| 壁紙・床 | 汚れ・傷みが目立つ場合 | 入居者へのイメージアップのため | 3~50万円 |
| 屋根・天井 | 屋根の穴やひび割れ、天井の一部に水漏れの跡がある場合 | カビ発生や雨漏りを防ぐため | 5~200万円 |
| 外壁 | 外壁を触ると手に白い粉が付くチョーキング現象やひび割れ、反りなどがある場合 | 防水性や耐候性を保ったり、外観を一新して雰囲気を変えるため | 20~500万 |
| 和室 | 全部屋が和室の場合 | 洋室があることで需要アップの可能性があるため | 30~100万円 |
とくに、水回りや内装は入居希望者の印象を左右するため、最低限のリフォームでも清潔感を出すことが大切です。費用を抑えたい場合はDIYを取り入れる方法もあります。リフォームで重要なのは、いかに「直さない部分を見極めるか」です。あれもこれもとこだわってしまえば、新築が買えるくらいの高額なリフォーム費用がかかります。
費用対効果を考慮し、必要最低限のリフォームから始めていきましょう。なお、リフォーム費用は施工会社(相見積もり推奨)や地域、空き家の状況などで変動するため、事前にチェックすることが大切です。
また、空き家特有のにおいやほこりを除去するため、クリーニングも忘れずに行いましょう。なお、一般的な戸建て(約30坪ほど)におけるクリーニング費用の目安は、約10万円(1㎡あたり1,000円ほど)です。
管理方法(自主管理 or 管理会社)の選定
空き家を賃貸に出す際に考えるべきなのが「管理方法」です。自分で対応する「自主管理」と、管理会社に任せる「管理委託」の2パターンが存在します。それぞれの特徴を比較してみました。
| 項目 | 自主管理 | 管理会社 |
| 費用 | 管理会社よりも安価 | 管理費が必要(目安は家賃の5%ほど) |
| 対応 | 入居者・トラブル対応などを自分で行う | 入居者・トラブル対応などをプロが行う |
| 集客 | 自分で行う | プロが代行して行ってくれる |
| 向いている人 | 自分の時間や知識、経験を活かして費用を抑えたい人 | 費用を払ってでも手間をかけたくない人 |
自分の時間・知識・経験を活かせる場合は、自主管理のほうが費用が抑えられるでしょう。ただし、遠方に住んでる、仕事が忙しくて時間が取れない、トラブル対応が不安という場合は、管理会社の活用が望ましいといえます。自分の状況に合った管理方法を選択することが大切です。
家賃相場の調査と設定
適切な家賃設定は、空室リスクを軽減するうえで非常に重要な要素です。高すぎれば入居が決まらず、安すぎれば収益性が下がってしまいます。まずは、家賃相場を調べる方法から見ていきましょう。
家賃相場を調べる方法は、主に2つあります。
- ポータルサイトや空き家バンクなどで、同じ地域や築年数、間取りの物件を検索し、家賃の平均を確認する
- 地元の不動産会社に相談し、リアルな相場感や過去の成約事例などを確認する
手軽に家賃相場を調べるのであれば、ポータルサイトや空き家バンクなどの情報を参考にすると良いでしょう。ただし、掲載されている家賃は相場に見合わない場合があるため、地元の不動産会社を活用して「実際に成約した家賃」を調べることも大切です。
次に、家賃を設定する際のポイントは、以下のとおりです。
- 周辺相場に見合った家賃設定にする
- 築年数、設備、立地、条件ターゲット層(単身・ファミリー・高齢者など)によって家賃の増減を調整する
- 初期費用(敷金・礼金)や管理費などを含めた総額で考える
- 空室リスクを想定した安めの家賃設定を行うのもあり
長期の空室リスクを抱えないためにも、適切な家賃設定を行いましょう。
賃貸借契約の準備
賃貸借契約は、トラブルを未然に防ぐための重要な手続きです。スムーズかつ正確に行うため、早めの準備を行いましょう。事前に準備すべき書類は、主に以下のとおりです。
| 書類 | 詳細 |
| 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーなど) | 不動産会社との契約時に必要 |
| 最新の登記簿謄本(全部事項証明書)※直近3か月以内が理想 | 空き家の所有者であることや権利関係を確認するときに使用 |
| 間取り図 | 借主募集時の広告に使用 |
| リフォーム履歴がわかる書類 | 広告の記載に使用 |
| 物件写真 | できる限り多めに、広告に使用する外観、内観、設備などを撮影 |
| 設備の取扱説明書 | 借主とのトラブル回避につながる |
| 管理規約(マンションの場合) | 共用部分の利用ルールや使用細則などをまとめたもの |
準備する書類は不動産会社によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
入居者の募集
「どのように入居者を集めるか」を決めましょう。入居者を募集する際は、以下のような方法があります。
| 募集方法 | 向いているケース |
| 不動産会社へ依頼 | ・早く確実に入居者を見つけたい ・手間をかけたくない ・幅広い層(単身者~ファミリー)へアプローチしたい |
| ポータルサイトに掲載 | ・広範囲から募集したい ・ネット経由で若年層やファミリー層をターゲットにしたい ・自主管理で費用を抑えたい |
| SNSの活用 | ・若年層(20~30代)にアピールしたい ・おしゃれなデザイン ・リノベ物件をPRしたい ・拡散力を重視したい |
| 地域密着型の掲示板・フリーペーパーの活用 | ・近隣に住む人(実家近くに住みたい層など)をターゲットにしたい ・シニア層や地域住民向けにアピールしたい |
| 現地看板の設置 | ・物件が交通量の多い道路沿いや住宅街にある ・近隣で物件を探している人へ直接アプローチしたい |
相性の良い方法を組み合わせることで、ターゲットごとに効率よく集客できます。たとえば、現地看板と地域密着型の掲示板を活用することで、近隣住民にアピールしやすいでしょう。また、SNSとポータルサイトを活用すれば、広範囲から借主を探すことが可能です。ターゲットに合う方法で効率よく集客しましょう。
入居者の審査
借主が現れたら、トラブル防止のために必ず審査を実施します。借主の信用調査は、家賃滞納やリスクを防ぐために非常に重要です。基本的には、以下のような項目が主な審査対象になります。
| 審査内容 | 詳細 |
| 本人確認 | 身分証明書が偽造されていないか(住所・氏名を確認) |
| 支払い能力 | 収入に対して家賃負担率が高すぎないか(30%以下が目安) |
| 勤務先や職業 | 安定した職業か、勤務年数は長いか |
| 保証人や保証会社 | 信頼できる保証人がついているか、または保証会社加入済みか |
| 過去の滞納歴 | 過去の家賃滞納履歴がないか |
| 人柄や態度 | 借主として常識的な人かどうか |
支払い能力や職業などのほかにも、不動産会社との対応や言葉遣いなどの人柄や態度も審査対象です。人柄や態度に問題がある場合は、貸主や近隣住民とトラブルを起こす可能性があるため注意が必要です。
借主による初期費用(敷金・礼金・仲介手数料・前家賃・日割り家賃・管理費・保証会社利用料など)の支払い方法は、銀行振込や現金支払いが一般的といえます。初期費用の支払いタイミングに関しては、入居審査から1〜2週間後に設定されることが多いでしょう。
賃貸借契約の締結・引き渡し
審査を無事に通過すれば、賃貸借契約を締結します。賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があることを覚えておきましょう。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 契約種別 | 特徴 | 向いているケース |
| 普通借家契約 | ・一般的な賃貸借契約・契約は口頭でも可能 ・借主の保護が手厚く、安心感がある ・最低契約期間は1年以上(通常2年契約が多い) ・1年未満の契約は「期間の定めがない賃貸借契約」になる ・期間満了後も借主が希望すれば更新が基本 ・貸主側が契約終了を希望する場合は、立ち退き料を求められるケースもある ・家賃の増減を請求できる ・中途解約に関する特約があれば従う | ・長期間に安定した家賃収入を得たい ・すぐに売却や自己利用の予定がない |
| 定期借家契約 | ・一定期間のみの賃貸借契約 ・更新はなく契約期間満了で終了 ・1年未満の契約も可能 ・契約時に「定期借家契約であること」を公正証書証書などの書面で交付、説明する義務あり ・引き続き住みたい場合は再契約が必要 ・家賃の増減は特約に従う ・床面積200㎡未満の居住用建物の場合、借主の転勤や親族の介護など、やむを得ない事情があれば、借主からの中途解約が可能 | ・一定期間後に空き家を売却したい ・親族や自身で使用するまでの期間限定で貸したい |
国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査 報告書」によれば、9割超が普通借家契約が締結されていることがわかります。定期借家契約を締結する理由(期間限定で貸したいなど)がなければ、普通借家契約の締結が望ましいでしょう。
続いて、賃貸借契約時に必要な書類や物は、主に以下のとおりです。
| 必要な書類・物 | 詳細 |
| 賃貸借契約書 | ・貸主、借主それぞれ2通 ・賃貸借契約の場合は収入印紙不要 |
| 重要事項説明書 | ・不動産会社経由の場合は、宅建士が記名した重要事項説明書の説明を行う ・直接契約の場合は、重要事項説明書は不要 |
| 物件の鍵 | スペアも用意しておくと安心 |
| 本人確認書 | 運転免許証やマイナンバーなど |
| 入居時物件状況チェックシート (現状確認表) | ・設備の状態や傷の有無をチェックして記録する ・退去時のトラブル防止に必須 |
| 口座情報 | 家賃の振込先口座を記載した用紙を契約時に渡すことで、家賃回収がスムーズになる |
不動産会社経由であれば、賃貸借契約書や重要事項説明書は用意してくれるでしょう。直接契約の場合、契約書のテンプレートは不動産会社や法務局、インターネットなどで入手可能です。ただし、賃貸借契約書の作成は法的な知識や経験が必要なため、トラブル防止のためにも専門家のチェックを受けておきましょう。
契約当日の流れ(不動産会社経由)は、主に以下のとおりです。
- 不動産会社の宅建士が重要事項説明を行い、内容を確認する
- 問題がなければ、借主が署名・捺印する
- 賃貸借契約書の内容を確認する
- 問題がなければ、貸主・借主が署名、捺印する
- 物件(鍵)の引き渡しを行う
賃貸借契約が無事に締結できれば、物件(鍵)の引き渡しを行い、一連の流れは完了です。
空き家を賃貸に出した際の税金・法律
空き家を賃貸に出すときに、切っても切れないのが法律や税金です。貸主に関わる法律や税金について少しでも知識を身に付けておくことで、節税効果が得られたりトラブル回避につながります。
空き家を賃貸に出して発生する税金と対策
空き家を賃貸に出して得られる家賃収入(不動産所得)は、所得税や住民税として課税対象になります。確定申告を行わなければ、無申告加算税や延滞税といったペナルティを受けるリスクも。家賃収入に関わる、以下の税金を覚えておきましょう。
| 税金 | 詳細 |
| 所得税 | 家賃収入から経費(固定資産税・管理費・修繕費・広告費など)を差し引いた不動産所得に対してかかる |
| 住民税 | 所得税の金額で算出される |
| 固定資産税・都市計画税 | 空き家を所有している限り発生する |
| 消費税 | 以下の場合に課税される ・人が住む「居住用物件」ではなく、店舗や事務所などの「事業用物件」かつ売上が1,000万円を超えている ・契約期間が1か月未満の居住用物件(ホテルや民泊扱い) |
また、空き家を本格的に賃貸運用するなら、節税対策として青色申告を検討する価値があります。最大65万円の控除が受けられるなど、白色申告よりも節税効果の大きさが強みです。青色申告と白色申告の比較は、以下のとおり。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
| 帳簿の記帳方法 | 複式簿記・単式簿記 | 単式簿記 |
| 特別控除額 | 最大65万円 | なし |
| 事前申請 | 必要(税務署に「青色申告承認申請書」提出) | 不要 |
| 赤字の繰越 | 最大3年間 | 不可 |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与:経費として全額計上可能 | 事業専従者控除:経費として一部(配偶者86万円・配偶者以外50万円/人)計上可能 |
| メリット | 節税効果が高いく、赤字も有効活用できる | 手続きが簡単で初心者向き |
| デメリット | 複式簿記など手間がかかる | 節税効果が少なく制限が多い |
青色申告は節税メリットが大きいものの、帳簿付けや申請の手間がかかります。ある程度の収益が見込め、長期運用を見据えた貸主におすすめといえるでしょう。税理士などの専門家に相談しながら、自分に合った申告方法を選ぶのがベストです。
民法改正による賃貸借契約のルール変更
2020年の民法改正により、賃貸借契約のルールが一部変更されました。法務省の「賃貸借契約に関するルールの見直し」によれば、「原状回復義務」や「敷金の返還」に関する条文が明文化され、貸主と借主のトラブル回避に役立っています。主なポイントは、以下のとおりです。
| 改正内容 | 変更点 |
| 原状回復義務の明確化 | 原則として借主に原状回復義務があるものの、「通常使用による損耗や経年劣化」に関しては対象外 |
| 敷金の定義 | 敷金は賃貸借終了後に返済義務が生じ、家賃未払い分を差し引いた残額であることを定義 |
| 賃借物の修繕に関する規定 | 賃貸人が修繕をしない場合や急迫の事情があるとき、賃借人自身による修繕が可能 |
| 賃貸不動産が譲渡された場合の対応 | 所有者が変わった場合、登記がされていれば新所有者が賃貸人となり、賃料請求が可能 |
| 個人保証契約における極度額の設定義務 | 個人が保証人になる根保証契約の場合、債務上限額(極度額)の明記が義務化 |
契約時には最新の民法に準拠した契約書を使用しましょう。
相続した空き家を賃貸に出すときのポイント
相続で得た空き家を賃貸に出す場合、「登記変更」や「遺産分割」が済んでいないと貸し出しできないケースもあります。おさらいも兼ねて、以下のようなポイントを意識しましょう。
| ポイント | 詳細 |
| 相続登記(名義変更)を済ませる | ・不動産の名義が亡くなった人のままだと、賃貸契約が締結できない ・相続登記は2024年4月から義務化されており、放置すると過料の対象に |
| 家屋の状態確認と修繕の必要性の確認 | ・長期間空き家だった場合、雨漏りやシロアリ被害の可能性あり ・設備不良がある可能性あり ・賃貸前にインスペクションを実施し、必要なリフォームを行う |
| 賃貸需要の確認と賃料相場の調査 | ・空き家がある地域で賃貸ニーズがあるかどうかを調査 ・周辺の賃貸物件と比較して、賃料や設備が競争力を持てるかも確認 |
| 賃貸経営としてのリスク認識 | ・空室リスクあり ・修繕費・滞納リスクなどが発生する可能性あり ・不動産管理会社に委託するか、自主管理するかで負担も変わるため、検討が必要 |
| 確定申告と税務の知識 | ・家賃収入があれば、不動産所得として確定申告が必要 ・固定資産税やリフォーム費用を計上することで節税できる場合もある |
| 敷金・原状回復など賃貸借契約ルールの理解 | ・民法改正(2020年施行)で原状回復や敷金返還のルールが明確化 ・トラブル防止のためにも、契約書の内容や借主との合意内容はしっかり明文化する |
| 家族間の合意形成 | ・相続人が複数いる場合、賃貸に出すことについて全員の合意が必要 ・トラブル防止のためにも、共有名義の整理や委任契約をしておくとスムーズ |
とくに、相続人間の意見が分かれている場合は、賃貸に出せるまで時間がかかります。最悪の場合は、賃貸に出せない可能性もあるでしょう。相続人同士で解決しない場合は、弁護士や司法書士に相談しながら進めると安心です。
空き家を賃貸に出したときのトラブル事例と対策
空き家を賃貸に出すと、以下のようなトラブルが起こることもあります。
- 家賃滞納トラブル
- 現状回復トラブル
- 近隣トラブル
- 契約トラブル
- 退去トラブル
- 空室トラブル
これらのトラブルを事前に理解しながら適切な対策を行い、リスクを最小限に抑えましょう。それぞれ解説します。
家賃滞納トラブルと対策
空き家を賃貸に出すとき、多くの貸主が心配する「家賃滞納」。家賃滞納が発生すると安定収入が得られないため、精神的なストレスを抱えることになるでしょう。家賃滞納トラブルの事例と対策は、以下のとおりです。
| 事例 | 対策 |
| ・借主の収入減や失業 ・支払いの優先順位が低下 ・借主との契約が曖昧 | ・家賃保証会社を利用する(契約時に審査あり) ・借主選定時に収入や職業、保証人の有無を厳しく確認 ・滞納時の対応フローを契約書に明記 |
とくに、家賃保証会社との契約をセットにすることで、家賃滞納リスクを軽減できます。仮に借主が家賃を支払わなかった場合でも、家賃や管理費、共益費などを保証してくれるのが一般的です。そのほか、退去時のクリーニング費用や原状回復費用などもカバーしている保証会社もあるため、必要に応じて選択すると良いでしょう。
原状回復トラブルと対策
退去時の原状回復を巡って、貸主と借主との間でトラブルになるケースも少なくありません。原状回復トラブルの事例と対策は、以下のとおりです。
| 事例 | 対策 |
| ・借主が退去時に、壁紙の変色や日焼けを理由に張替え費用を請求された ・家具の設置によって生じた床やカーペットのへこみについて、借主に修繕費用が請求された ・退去時に、エアコンの内部洗浄費用が借主に請求された | ・通常の使用による経年劣化や損耗に関しては、借主の負担には該当しないことを理解しておく ・借主の使用方法に問題がある場合は、責任と負担が発生することも理解しておく ・契約前に「どこまでが入居者の負担なのか」を明確にする |
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」を参照し、貸主・借主負担になる部分や状況を把握しトラブル防止に役立てましょう。
近隣トラブル事例と対策
ゴミ出しのルール違反や騒音問題など、借主のマナーが原因で近隣住民とのトラブルに発展することがあります。結果的に、物件の評判が落ちて賃貸経営に悪影響を及ぼすリスクがあるでしょう。近隣トラブルの事例と対策は、以下のとおりです。
| 事例 | 対策 |
| ・ゴミを決められた日以外に出す ・ベランダ喫煙で苦情が出る ・ペットの騒音・糞尿の放置 | ・契約書にルールを詳細に記載する ・トラブル発生時は、すぐに管理会社または貸主が介入する ・定期的な巡回や近隣ヒアリングを実施する |
近隣トラブルを事前に防ぐには、契約書でルールを詳細に明記したうえで、借主の理解を得られるように説明することが大切です。さらに、日々の定期的な巡回や近隣ヒアリングも行えば、近隣トラブルの早期発見・対策が可能になります。
契約トラブル事例と対策
書面での契約を怠り、口約束で進めた場合、後から「言った・言わない」のトラブルに発展することがあります。契約トラブルは、貸主にとって非常にリスクが高いといえるでしょう。契約トラブルの事例と対策は、以下のとおりです。
| 事例 | 対策 |
| ・家賃の値引きを口頭で約束 →契約書に記載なし ・ペット飼育OKと聞いた →証明できない | ・必ず契約書にすべての条件を記載する ・特約で細かな条件も網羅しておく ・サイン済みの書面を保管し、PDF化して共有 |
どんなに親しい相手であっても、賃貸契約は「ビジネス」として扱うべきです。書面で残すことこそが最大の対策になります。
退去トラブル事例と対策
退去の際に立ち合いを行わず、後で「傷があった」「なかった」で揉めることは珍しくありません。スムーズな退去には、事前の準備と当日の確認がカギとなります。退去トラブルの事例と対策は、以下のとおりです。
| 事例 | 対策 |
| ・敷金の返還額や返還時期に関する不透明さから、借主が不満を持つ ・借主が家具やゴミなどを置いたまま退去し、処分に困る ・借主が立ち会いを拒む、または急なキャンセルを繰り返す | ・契約書に退去時の条件を具体的に明記しておく ・退去時に立ち会って現状確認する ・代理人や不動産会社に対応してもらう |
また、立ち合い後に「退去立会確認書」を交わすことで、双方が状態に納得した証拠を残せます。退去立会確認書で確認する内容は、主に以下のとおりです。
- 電気や水道、ガスなど使用料金の精算状況
- 鍵や貸出物(リモコン類・取扱説明書)の返却状況
- 工事内容(例:ハウスクリーニング) など
「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」も併用すれば、後日のトラブル防止に非常に効果的です。
空室トラブル事例と対策
空き家を賃貸に出したものの、長期間入居者が決まらず収益が得られないケースは少なくありません。とくに、築年数が古かったり管理状態が悪かったりすると、空室期間が長引く傾向にあります。空室トラブルの事例と対策は、以下のとおりです。
| 事例 | 対策 |
| ・周辺相場より家賃が高く、内見がほとんど入らない ・築古のため印象が悪く、写真の段階で敬遠される ・募集方法が限定的で、ターゲットに届いていない | ・家賃相場を事前に調査し、設備や築年数に応じた適正価格を設定する ・最低限のリフォームやクリーニングを行い、内装写真の質を上げる ・不動産会社、ポータルサイト、SNS、現地看板など複数の手段を併用する |
空室対策は、単に家賃を下げることではなく「選ばれる物件」に整えることが重要です。初期投資を抑えつつも、魅力を伝える工夫を積み重ねていくことが空室リスクを軽減する近道といえるでしょう。
空き家賃貸で失敗しないための運用・管理のコツ
空き家を貸し出したあとも、安定した賃貸経営を継続するためには「運用・管理の質」が非常に重要です。入居者との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐ体制を整えることで、空室や損害のリスクを最小限に抑えることができます。
定期的な点検・メンテナンスを欠かさない
建物の老朽化は避けられない問題です。雨漏りや配管の劣化、シロアリなどの定期点検を行うことで重大な損傷を未然に防ぐことができます。少なくとも年に1回はプロによる点検を行い、必要に応じて修繕や補強を行いましょう。定期的な点検・メンテナンスにより、借主の満足度も向上します。
トラブル対応マニュアルを用意する
「水漏れが起きた」「隣人と騒音トラブル」など、日常的に起こりうるトラブルに備えて、迅速に対応できるマニュアルを用意しておくと安心です。対応の流れや連絡先を明確にしておくことで、借主からの信頼にもつながります。管理会社に依頼している場合は、対応スピードの確認もしておきましょう。
家賃滞納への備えを強化する
家賃滞納は賃貸経営にとって深刻なリスクです。家賃保証会社の導入や、契約時に支払い遅延時のペナルティ規定を設けるなど、事前の対策が不可欠です。さらに、滞納が発生した場合の対応フロー(督促→内容証明→契約解除)をあらかじめ決めておきましょう。
入居者との円滑なコミュニケーション
賃貸経営において、入居者との良好な関係づくりは安定運用の基本です。定期的にアンケートや点検のお知らせを送り、顔が見える関係を築くことで、信頼と満足度が高まります。入居者からの要望には迅速かつ丁寧に対応する姿勢も重要です。
長期的な修繕計画を立てる
突発的な修繕費用は経営を圧迫する原因となります。そのため、10年単位での修繕計画(外壁塗装、屋根補修、水回り更新など)を立てておくと、予算管理もスムーズです。事前に見積もりを取得し、修繕積立の考え方を取り入れると安心といえます。
賃貸管理会社との連携を強化する
管理を外部に委託している場合は、管理会社とのコミュニケーションが鍵となります。定期的な報告体制や緊急時の連絡ルールを明確にしておくことで、トラブルへの初動対応も迅速に行えます。管理内容と費用のバランスも定期的に見直しましょう。
賃貸リスクを事前に洗い出す
トラブルの多くは「想定外」から始まります。入居者属性によるリスク(高齢者・外国人・単身者など)、物件の老朽化や設備不良、地域特有の問題(騒音、治安)などをリストアップし、事前に対応策を練ることがリスク管理の第一歩です。
自然災害への備えも万全に
台風、地震、大雨といった自然災害は、建物に大きな被害を与えるリスクです。火災保険や地震保険の加入はもちろん、ハザードマップでリスクを把握しておきましょう。耐震補強や排水対策を施すことで、損害を最小限に抑えられます。
保険へ加入する
保険加入は空き家賃貸における「防衛手段」です。火災・地震保険に加え、家賃保証保険や施設賠償責任保険なども検討しましょう。万一のトラブル時に迅速に対応するため、保険内容をきちんと把握し、更新を忘れず行うことが大切です。
契約トラブルを防ぐ
契約時にトラブルを避けるには、曖昧な表現を避けた明確な契約書が必須です。敷金・礼金、退去時の原状回復、ペット可否、禁止事項などは詳細に記載しましょう。また、契約時には重要事項説明を丁寧に行い、書面で確認を残すようにしてください。
騒音・近隣トラブルの未然防止
入居者同士や近隣住民とのトラブルを防ぐためには、騒音やゴミ出しマナーなど生活ルールを明確にすることが重要です。入居時にルールブックを配布する、掲示板で注意喚起するなど、周囲との良好な関係づくりを意識しましょう。
夜逃げ・孤独死など深刻リスクの対応
近年では孤独死や夜逃げといった深刻なトラブルも増えています。家賃保証会社の利用や見守りサービスの導入、定期的な連絡確認を行うことでリスクを最小化できます。とくに、高齢者を対象とする場合は事前の対策が重要です。
弁護士や専門家との連携体制を整える
万が一法的トラブルが起きた際に備えて、不動産に強い弁護士との関係を構築しておくと安心です。不動産管理会社経由で紹介してもらう方法もあります。賃貸契約や強制退去、損害賠償など、専門的判断が必要な場面では早期の相談がトラブルの長期化を防いでくれるでしょう。
空き家を賃貸に出すときのFAQ
空き家を賃貸に出すにあたって、よく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。空き家を賃貸に出す方が抱える不安や疑問点に対して回答しています。
- Q空き家を貸すのに資格は必要ですか?
- A
特別な資格は不要です。ただし、賃貸借契約書の作成やトラブル時の対応など、専門知識が必要な場面もあるため、不動産会社や専門家のサポートを受けると安心です。
- Q築年数が古い空き家でも貸せる?
- A
築年数が古くても需要があります。とくに、DIY物件やレトロ住宅を好む層、高齢者や単身者などがターゲットになる場合も。ただし、安全性と最低限の住環境の整備は必須です。
- Q家賃はどうやって決めればいい?
- A
地域の賃貸相場を参考にし、建物の状態や立地、周辺設備を考慮して設定します。不動産会社に査定を依頼したり、類似物件の情報をネットで確認する方法が一般的です。
- Q空き家を賃貸に出したら確定申告は必要?
- A
家賃収入がある場合は原則として確定申告が必要です。経費として控除できる項目(修繕費、管理費、保険料など)も多いため、節税効果も期待できます。税理士に相談するのが確実です。
- Qトラブルが怖いのですが、どう防げますか?
- A
契約前の入居者審査や保証会社の利用、明確な契約書の作成が効果的です。さらに、管理会社を活用することでトラブル時の対応もスムーズになります。予防と対応、両面から備えておきましょう。
- Q空き家を貸す際に自治体の支援はありますか?
- A
あります。空き家バンク制度や改修費補助、移住支援など自治体ごとに多彩な支援策が用意されています。自治体のホームページや相談窓口で確認してみましょう。
空き家の賃貸に活用できる補助金
空き家を賃貸物件として活用する際、リフォームや設備投資にかかる費用を抑えるために、補助金を活用できることがあります。実施されている補助金を、用途や要件とともに一覧表でわかりやすく紹介するので、ぜひ活用してみてください。
| 補助金名 | 主な用途 | 主な要件 | 補助額(補助率) |
| 岐阜県飛騨市「空き家賃貸住宅改修事業補助金」 | 空き家の賃貸活用に向けた改修 | 飛騨市住むとこネットに賃貸物件として登録すること など | 上限300万円 (1/2以内) |
| 福井県福井市「空き家リフォーム支援事業」 | 空き家の改修 | 福井市空き家情報バンクに登録された空き家であること など | 対象工事費の5分の1かつ上限30万円 |
| 大阪市「空家利活用改修補助制度」 | 空き家の改修 | 不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること など | 上限100万円(1/2) |
| 千葉県市川市「危険コンクリートブロック塀等除却事業補助金」 | 老朽化したブロック塀の撤去 | 耐震対策としてブロック塀を撤去すること | 上限30万円(2/3) |
補助金は地域によって内容や条件が異なるため、活用前には必ず各自治体や関係機関に確認するようにしましょう。また、複数の制度を組み合わせて使うことも可能な場合があるため、専門家に相談しながら進めるとより効果的です。
ポイントを抑えて空き家の賃貸を成功させよう!
空き家を賃貸に出すことは、社会問題化する空き家の増加に対する有効な対策であり、所有者にとっても維持管理コストの削減や収益化が期待できる手段です。ただし、実際に活用するためには、物件の状態確認やリフォームの実施、適法性の確認、借主の募集や管理体制の整備など、事前にクリアすべき課題が多く存在します。
さらに、立地条件によっては民泊やシェアハウスなど多様な活用法も選択肢となり得るため、物件ごとの特性を見極めた上で、適切な戦略を立てることが重要です。トラブル防止のためには、賃貸契約の種類(普通借家契約・定期借家契約)や内容についても慎重な検討が必要になるでしょう。だからこそ、信頼できる不動産会社や空き家活用の専門家との連携が成功の鍵を握ります。
空き家は放置すればするほど、資産価値が下がり管理コストが増大するリスクがあります。だからこそ、所有者としては「どう活用すべきか」を早期に判断し、計画的な準備をもって賃貸活用へと進めることが、空き家を資産に変える第一歩となるでしょう。