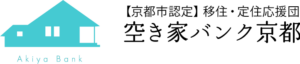- 保険に入るべきか迷っているものの、必要性がよく分からない
- 空き家を持っていて、火災や地震のリスクが気になる
- もし災害が起きたときに、補償を受けられるのか不安
空き家所有者は、建物のリスクを理解して適切な保険に加入することが大切です。万が一の事態に備えていなければ、修繕費が高額になったり、近隣への損害賠償責任を負ったりする可能性もあります。適切な保険がなければ、予想外の金銭的負担を抱えることになりかねません。
今回は、空き家に火災保険は必要か、地震保険に加入できるのか、加入時のポイント、補償範囲、保険料の相場などを詳しく解説します。当記事を読むことで、空き家のリスクを最小限に抑え、安心して管理するための知識が得られるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
空き家にも火災保険が必要な理由
結論として、空き家にも火災保険は必要といえます。火災保険が必要な理由としては、以下のとおりです。
| 理由 | 詳細 |
| 火災や放火のリスクが高い | 管理されていないと不審火や放火のターゲットになりやすい |
| 地震や自然災害による倒壊の危険性が高い | 台風・地震・豪雨などで損壊する可能性が高くなる |
| 隣家や通行人への損害賠償リスクがある | 火災や倒壊などで隣家や通行人などに被害を与えた場合、多額の賠償責任が発生する可能性あり |
| 建物の劣化・破損による修繕費負担がある | 放置すると修繕費用がかさみ、自己負担が大きくなる |
| 賃貸や売却時の資産価値を維持するため | 無保険のままだと価値が下がり、買い手や借り手がつきにくくなる |
| 保険未加入だと災害時の補償を受けられない | 修理費や再建費が全額自己負担になるリスクがある |
| 管理不足による保険適用外を防ぐため | 適切な管理がされていないと、保険金が支払われないケースがある |
空き家には、一般的な居住用物件とは異なり、特有のリスクが発生するため、いざというときの備えが必要です。火災保険に加入していない空き家の所有者は、検討してみてください。
火災・地震リスクが高まる空き家の特徴
火災・地震の被害を受けやすい空き家の特徴は、以下のとおりです。
| 特徴 | 詳細 |
| 老朽化が進んでいる | 長期間放置された空き家は、建材の劣化が進み、耐火性・耐震性が低下。地震時の倒壊リスクが高くなる。 |
| 木造住宅である | 木造建築は火が燃え広がりやすく、放火のリスクが高い。また、地震の揺れに弱く、倒壊の危険性が増す。 |
| 定期的な管理がされていない | ゴミや落ち葉などが溜まれば、放火や自然発火の原因になりやすい。長期間放置されることで、不審者が侵入しやすくなり、放火や不法投棄などの犯罪リスクが高まる。 |
| 周囲に可燃物が多い | 庭に枯れ草や古い木材が放置されていると、火災が発生した際に延焼しやすい。隣家との距離が近いと、火災が広がる危険性が増す。 |
| シロアリ被害や腐食がある | 基礎や柱がシロアリ被害を受けると、耐久性が低下し、地震時に倒壊の危険が高まる。また、雨漏りによる腐食が進むと、木材がもろくなり、火災発生時に燃えやすくなる。 |
| 設備の老朽化 | 古い電気配線のショートや漏電が火災の原因になる。ほかにも、老朽化したガス設備がガス漏れを引き起こし、引火・爆発のリスクが高まる。 |
| 耐震基準を満たしていない | 古い空き家は、現行の耐震基準を満たしておらず、地震時の倒壊リスクが高い。耐震補強がされていないと、大きな揺れに耐えられず被害が拡大する可能性がある。 |
これらの特徴に当てはまる空き家は、火災・地震リスクが高まりやすいといえます。火災・地震リスクを避けるためにも、空き家の適切な管理や保険の加入が大切です。
火災保険とは?基礎知識を学ぼう
火災保険は、火災や自然災害などによる損害を補償する保険です。住宅の所有者が加入し、建物や家財の損害をカバーします。火災だけでなく、落雷・爆発・風災などの被害も補償対象となるため、住宅を守るために欠かせない保険の一つです。
火災保険の仕組み
火災保険は、契約者が支払う保険料に応じて、火災やその他の自然災害による損害を補償します。補償内容は契約内容によって異なり、必要な補償範囲を選択することが可能。補償額は、住宅の構造や所在地、補償内容によって決まります。契約期間は1年から最長5年(22年10月より)まで選べるのが一般的です。
火災保険は、基本的に何度も利用できます。ただし、以下の場合には契約が終了したり、保険料が上がったりするので覚えておきましょう。
- 全損の場合
- 契約保険金額の80%を超える支払いがある場合
- 頻繁に保険料の支払いが発生する場合
住宅ローンを組む際には、火災保険の加入が必須となる場合が多いため、事前に確認しておきましょう。なお、地震による火災は火災保険の対象外となっているため、別途、地震保険に加入しなければいけません。
火災保険の補償対象
火災保険の補償対象は、大きく分けて「建物」と「家財」の2つです。建物とは、住宅そのもの(柱・壁・屋根など)を指し、家財は室内にある家具・家電・衣類などの生活用品を含みます。火災保険に加入する際は、建物のみを対象にするか、家財も含めるかを選択することが可能。賃貸住宅の場合、建物は大家が加入するため、入居者は家財保険に加入するのが一般的です。
火災保険で補償される主な範囲
火災保険は、火災以外にもさまざまな災害を補償します。主な補償範囲は、以下のとおりです。
- 火災:失火、放火など
- 騒擾:集団行動による暴力行為による損害等
- 落雷:落雷による家電製品の故障など
- 水災:洪水・土砂崩れなど(オプションの可能性あり)
- 爆発・破裂:ガス爆発等による損害
- 盗難・破損:泥棒による家財の盗難や破損
- 風災・雹災・雪災:台風、竜巻、豪雪などによる損害 など
補償の範囲は保険会社やプランによって異なるため、契約前に確認するようにしましょう。
火災保険の補償対象外になる主なケース
火災保険では、すべての損害が補償されるわけではありません。以下のケースは、補償対象外となる可能性があります。
- 地震・噴火・津波が原因の火災
→ 地震保険に加入が必要 - 故意や重大な過失による火災
→ 放火や管理不足による火災 - 経年劣化による損害
→ 老朽化による建物の倒壊や雨漏りなど - 大規模な暴動による損害
→ 戦争やテロなど - 免責金額に満たない損害
→ 例:免責金額10万円の場合は、10万円以下の損害では火災保険が受け取れない
補償範囲を正しく理解し、状況に応じて必要な特約を追加することが大切です。
火災保険料の相場
火災保険料の一般的な相場は、以下のとおりです。
| 構造 | 保険料相場(年間) |
| 木造(W造) | 約2~5万円 |
| 鉄骨造(T造) | 約1.5~4万円 |
| 鉄筋コンクリート造(M造) | 約1~3万円 |
火災保険料は、所在地や建物の構造、築年数、保証範囲、契約年数などの要因で異なります。たとえば、火災リスクが高い木造では保険料が高くなりがちです。一方で、火災リスクの低い鉄筋コンクリート造であれば、保険料が安くなりやすいといえます。事前に保険会社のシミュレーションを行い、保険料を比較することが大切です。
地震保険とは?基礎知識を学ぼう
地震保険は、地震・噴火・津波による住宅の損害を補償する保険です。火災保険と異なり、地震による火災や倒壊は補償対象外となるため、地震リスクの高い地域では地震保険の加入が推奨されます。日本は地震大国といわれるほど、地震が多い国です。万が一の損害に備えて大切な住宅を守りたい場合は、地震保険の加入も検討すると良いでしょう。
地震保険の仕組み
国と民間の保険会社が共同で運営しており、補償内容や保険料は共通(払込方法によって保険料が異なる場合あり)です。保険料は国が定めており、地域や建物の構造によって異なります。補償額は火災保険の30〜50%(居住用物件:5,000万円、家財:1,000万円)が上限となり、以下のように全損・一部損などの被害状況に応じて支払われます。
| 損害状況 | 損害認定基準 | 支払保険額 | |
| 建物 | 家財 | ||
| 全損 | 【主要構造部の損害額】建物時価額50%以上 | 【家財損害額】家財時価総額80%以上 | 地震保険金額100%(上限:時価額) |
| 【焼失・流出部分の床面積】建物延床面積70%以上 | |||
| 大半損 | 【主要構造部の損害額】建物時価額40~50%未満 | 【家財損害額】家財時価総額60~80%未満 | 地震保険金額60%(上限:時価額60%) |
| 【焼失・流出部分の床面積】建物延床面積50~70%未満 | |||
| 小半損 | 【主要構造部の損害額】建物時価額20~40%未満 | 【家財損害額】家財時価総額30~60%未満 | 地震保険金額30%(上限:時価額30%) |
| 【焼失・流出部分の床面積】建物延床面積20~50%未満 | |||
| 一部損 | 【主要構造部の損害額】建物時価額3~20%未満 | 【家財損害額】家財時価総額60~80%未満 | 地震保険金額5%(上限:時価額5%) |
| 【全損、大半損、小半損、一部損以外】床上浸水、地盤面から45cm以上の浸水 | |||
参考元:損害保険料率算出機構|地震保険基準料率
地震発生後、一定の基準で被害認定が行われ、保険金が支払われる仕組みです。
地震保険の対象(建物・家財)
地震保険の対象も、火災保険と同様に建物と家財に分かれます。建物とは住宅そのものを指し、家財は家具や家電、衣類などを含みます。ただし、貴金属・骨董品・自動車などは補償対象外となるため、別の保険でカバーする必要があります。
地震保険で補償される主な範囲
地震保険は、主に以下のような被害を補償します。
- 地震による建物の倒壊、火災の損害
- 地震による洪水、津波の損害
- 地震による土砂災害の損害
- 噴火による倒壊、埋没 など
なお、補償は全額ではなく、火災保険の最大50%まで。万が一の際に十分な補償が受けられるか、事前に確認することが重要です。
地震保険の補償対象外になる主なケース
地震保険では、主に以下のケースは補償されません。
- 事務所や工場などの事業用建物
- 地震以外の原因による損害(火災・風水害など)
- 地震発生後の盗難被害
- 家財の一部損壊(一定の基準未満の場合)
- 地盤沈下や液状化による影響(基準を満たさない場合) など
契約内容によっては特約で補償できる場合もあるため、補償内容をしっかり確認することが大切です。
地震保険は火災保険とセットでしか加入できない
地震保険は単独での加入はできず、火災保険とセットで契約することで補償を受けられます。主な理由としては、以下のとおりです。
- 地震による被害や損害額の予測がしにくいこと
- 「被災者の生活を安定させることが目的」のため、火災保険の付帯として地震保険単独のコストを抑える仕組みであること
地震保険は、火災保険に加入している途中でも契約できます。地震リスクの高い地域では、万が一の備えとして早めに加入を検討しましょう。
地震保険料の相場
地震保険料の一般的な相場は、以下のとおりです。
| 都道府県 | 保険料相場(年間) |
| 木造(W造) | 約1~4万円 |
| 鉄骨造(T造)鉄筋コンクリート造(M造) | 約5千~2万円 |
地震保険料は、所在地や建物の構造、契約金額、契約年数などの要因で異なります。たとえば、地震リスクが高い地域(東京都や千葉県など)かつ契約金額が多いと保険料が高くなりがちです。
一方で、地震リスクが低い地域(北海道や福岡県など)かつ契約金額が低ければ、保険料が安くなりやすいといえます。火災保険と同様に、シミュレーションを行うと良いでしょう。
空き家でも火災・地震保険に加入できる?
空き家であっても、建物の状態や使用状況などによって火災保険に加入できます。以下の条件に当てはまる空き家は、居住用物件の火災保険に加入できる可能性があります。
- 家財が常時備えられている
- 別荘として定期的に使用している
- 転勤等の理由で一時的に空き家になっている
- 賃貸物件として入居者を募集している など
また、「一般物件(居住用以外の店舗や事務所など)」の空き家に該当すれば、火災保険に加入できる可能性も。条件としては、今後も住む予定がなかったり、入居者募集をしていなかったりすることが挙げられます。ただし、一般物件の場合は、保険料が居住用物件よりも高めなので注意が必要です。
火災保険に関しては、保険会社によって空き家に適した(専用もある)の保険があることも覚えておきましょう。たとえば、空き家・空き地管理センターでは、日新火災海上保険株式会社との提携により、空き家専用保険を提供。解体費用や賠償責任などの補償といった、空き家ならではのリスクに備えた内容になっているのが特徴です。
一方、一般物件の空き家として火災保険に加入している場合は、地震保険に加入できません。地震保険は、あくまで「被災者の生活を安定させる目的」があるため、人が居住していない空き家には適用されません。そのため、定期的な修繕や耐震補強などで対策する必要があります。
空き家の火災保険に加入する主な流れ
空き家の火災保険に加入する主な流れや必要書類を解説します。火災保険に加入させる際の主な流れと必要書類は、以下の通りです。
- 事前相談
- 相見積もり
- 選定
- 契約内容の確認
- 契約
それぞれを見ていきましょう。
1.事前相談
契約している保険会社、もしくは新たに契約を検討している保険会社に、物件が空き家である旨を伝え、加入可能かを確認します。
2.相見積もり
加入可能な複数の保険会社に見積もりを出してもらい、ご自身や物件に最適な火災保険を検討してください。見積もりの際には、所在地・延床面積・建築年月・建物の構造がわかる以下の書類が必要です。
- 売買契約書
- 建築確認申請書
- 仕様書 など
3.選定
相見積もりの結果や補償内容などを考慮し、ご自身や空き家の状態に最適な火災保険を選びましょう。
4.契約内容の確認
保険料や補償範囲などの契約内容を、しっかり確認し、契約するかどうかを検討します。
5.契約
契約内容に問題がなければ、契約を進めます。契約時には、以下の書類を求められることが一般的です。
| 戸建ての場合 | 登記簿謄本、建築確認申請書、確認済証など |
| マンションの場合 | 登記簿謄本、重要事項説明書、登記事項証明書など |
| 耐火性能を証明する場合 | 建築確認申請書、仕様書、建築構造証明書など |
| 火災保険を乗り換える場合 | 保険証券、保険契約継続証、保険契約証など |
※各種書類は法務局やハウスメーカーなどで取得可能
空き家で火災保険に加入する際の注意点と対策
空き家で火災保険に加入する際は、いくつかの注意点があります。これまで解説した内容も含めて、注意点と対策をまとめてみました。主な注意点と対策は、以下のとおりです。
| 注意点 | 詳細 | 対策 |
| 火災保険に加入できない可能性がある | 居住用物件の火災保険は「人が住んでいること」が前提になっているため、無人の空き家は対象外となる場合がある。 | 空き家専用の火災保険、一般物件の火災保険を検討する。 |
| 保険料が割高になる可能性がある | 空き家はリスクが高いため、通常の住宅より保険料が高額になる傾向がある。 | 長期契約、不要な補償を外す、契約保険金額を低くする、保険会社の割引を活用する。 |
| 補償内容が限定される場合がある | 居住用物件の火災保険よりもリスクが高くなることから、補償範囲が狭くなる可能性がある。 | 事前に火災保険の内容を確認したり、空き家専用の火災保険を検討したりする。 |
| 建物の状態によっては加入できないこともある | とくに老朽化が進んだ空き家は、倒壊や火災のリスクが高いため、保険の引き受けを拒否される可能性がある。 | 定期的な管理や修繕を行い、空き家の老朽化を抑えたり、原状回復したりする。 |
| 一般物件の火災保険に加入している空き家は、地震保険に加入できない | 地震による被災者の生活安定を目的としているため、一般物件の火災保険に加入している空き家には地震保険が適用されない。 | 耐震補強や修繕を行い、地震に対する耐震強度の維持や向上を行なう。 |
| 既存の火災・地震保険が適用されなくなる可能性がある | 既存の火災・地震保険に加入していたとしても、空き家の管理状況や状態によっては、適用されなくなる可能性がある | 空き家になった場合に、保険会社に連絡して、現状の確認やアドバイスをもらう。 |
空き家の火災保険を選ぶ際のポイント
空き家の火災保険を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
- 空き家専用の火災保険があるかを確認する
- 火災以外の補償内容をチェックする
- 保険の適用条件や免責事項を確認する
- 賠償責任補償の有無を確認する
- 既存の火災保険を見直してみる
それぞれ解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
空き家専用の火災保険があるかを確認する
空き家専用の火災保険を提供している保険会社を選ぶことが重要です。空き家は居住用物件と比べて火災リスクが高いため、一般的な火災保険では補償の対象外になることがあります。
空き家専用の火災保険では、火災に伴う解体費用や見舞金、賠償責任補償などを受けられる場合があるでしょう。まずは、空き家でも契約可能な保険商品を比較し、自分の状況に最適なものを選んでください。
火災以外の補償内容をチェックする
火災保険以外の補償内容をチェックしましょう。火災保険は、火災以外にも落雷・爆発・風災・水災・盗難などの補償が含まれている場合があります。空き家は適切な管理が難しいため、より自然災害や放火などのリスクも考慮する必要があるでしょう。
たとえば、台風や洪水で建物が損壊した場合、火災保険の補償範囲に含まれていなければ自己負担になってしまいます。契約前に、火災以外のリスクにも対応できる補償内容を選ぶことが大切です。
火災保険の適用条件や免責事項を確認する
空き家の火災保険は、適用条件や免責事項に該当しなければ、保険料が支払われない可能性があります。たとえば、老朽化による倒壊や設備の不具合による火災などは、免責事項として補償対象外になることも。
とくに、空き家の場合は居住用物件の火災保険よりも適用条件や免責事項が特殊な場合があります。契約前に、適用条件や免責事項をしっかり確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。
賠償責任補償の有無を確認する
火災保険に賠償責任補償が含まれているかを確認することが重要です。空き家で火災が発生し、近隣住宅へ延焼した場合、所有者には多額の損害賠償責任が発生する可能性があります。
たとえば、第三者に被害を与えた場合に適用される「施設賠償責任保険」に加入できるかをチェックしましょう。万が一のトラブルに備え、適切な賠償責任補償が受けられる保険を選ぶことが大切です。
既存の火災保険を見直してみる
既存の火災保険に加入している場合、その補償内容が空き家にも適用されるかを確認しましょう。居住用として加入していた保険が、一定期間無人になることで補償対象外になることがあります。
また、特約を追加することで空き家でも補償を受けられる場合もあるでしょう。新規加入を検討する前に、現在の保険内容を確認することが大切です。必要に応じて見直しやオプション追加を検討すると、無駄な出費を抑えながらリスク管理が可能になります。
保険以外でできる空き家の火災・地震リスク対策
火災や地震リスクを最小限に抑えるには、保険に加入するだけでなく、日常的な管理や活用を検討することが重要です。以下の空き家の火災・地震リスク対策も検討してみましょう。
- 定期的な修繕や清掃
- 防犯設備の設置や巡回
- 空き家の利活用
それぞれ解説します。
定期的な修繕や清掃
空き家の火災・地震リスクを軽減するためには、定期的な修繕や清掃が不可欠です。屋根や外壁の劣化を放置すると、強風や地震で倒壊の危険が増します。また、枯れ葉やゴミが溜まると火災の原因になりかねません。
室内の換気や水回りを怠ると、湿気やカビの発生原因になります。最低でも年に数回は点検を行い、適切な修繕や清掃を実施することで、空き家の倒壊リスクを抑えながら寿命を延ばせるでしょう。
防犯設備の設置や巡回
空き家は不審者や放火犯の標的になりやすいため、防犯対策が重要です。センサーライトや防犯カメラを設置することで、不審者の侵入を防ぐ効果が期待できます。
また、郵便物の放置を避けたり、庭の手入れを行ったりすることで「管理されている家」として犯罪抑止につながるでしょう。地域住民や警備会社と協力し、定期的な巡回を実施することも、不審者の侵入を防ぐ有効な手段です。
空き家の利活用
長期間放置された空き家は、火災や地震リスクが高まるため、利活用を検討することが重要です。賃貸物件として貸し出せば、適切な管理が継続され、建物の老朽化を防ぐことができます。
売却すれば所有リスクがなくなり、維持費や税負担を軽減することが可能です。また、地域のコミュニティスペースやシェアハウスとして活用することで、防犯対策にもなり、空き家の価値を高めることができます。
空き家にも火災保険を適用させてリスク管理しよう!
空き家にも火災保険を適用させることで、火災や自然災害による損害リスクを軽減し、資産を守れます。老朽化や放置により火災・倒壊のリスクが高まるだけでなく、近隣への損害賠償責任も発生する可能性があるため、適切な保険加入が不可欠です。
また、定期的な管理を行いつつも、空き家の利活用を検討しましょう。リスクの高い「負動産」から、収益を生んでくれる「富動産」に生まれ変わる可能性があります。ぜひ、不動産会社や専門家に、空き家の利活用を相談してみてください。